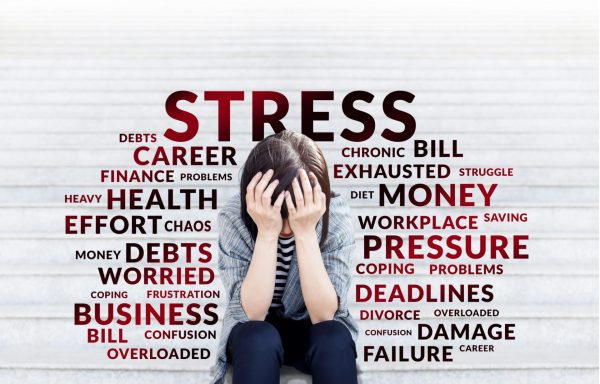Blog ブログ
タグ
#虫歯
北名古屋市 乳幼児健診・むし歯予防教室
こんにちは、水野歯科クリニックです。 全国の市区町村において歯科保健事業が行われています。 もちろん北名古屋市も行事予定が組まれております。 ☆北名古屋市 母子健康保険事業のお知らせ☆ 問診票は手帳内にあります。 〇1歳6か月児検診 10/6(金) 10/20(金) 〇2歳児むし歯予防教室 10/5(木)11/9(木) 〇2歳6か月児むし歯予防教室 10/19(木) 〈持ち物 母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本〉 ●3歳児健診10/12(木) 10/26(木) 〈持ち物 母子健康手帳、問診票、視力・聴力検査結果票(すこやか手帳内)、バスタオル、歯ブラシ1本 ※視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。〉 ところ 健康ドーム お問い合わせ 健康課(保健センター 健康ドーム内) 電話:0568-23-4000 ファクス:0568-23-0501 E-mail:[email protected] 当院は日本歯科医師会及びその下部組織の愛知県歯科医師会及び西春日井歯科医師会に所属しております。 歯科医師会では、毎年地域の皆様への口の中に対する啓蒙活動、北名古屋市の乳幼児健診・むし歯予防教室も行っています。 水野歯科クリニック 第二種歯科感染管理者 水野明里
8020(はちまるにいまる)達成者は2人に1人以上 過去1年間に歯科検診を受診した人は約6割
こんにちは水野歯科クリニックです。 先月の話ですが 厚生労働省は6月29日、「令和4年歯科疾患実態調査」の結果(概要版)を取りまとめ、公表しました。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33814.html https://www.mhlw.go.jp/content/10804000/001112405.pdf 出典元:厚生労働省 この歯科疾患実態調査というものは 国民生活基礎調査の際に一緒に調べられるもので <調査期間>令和4年11月~12月 <調査対象>令和4年国民生活基礎調査で設定された地区(令和2年国勢調査の調査区から層化無作為抽出した全国5,530地区)から抽出した300地区内の世帯の満1歳以上の世帯員(被調査者数は2,709人) <調査方法>調査対象地区内の会場で、歯科医師が調査対象者の口腔診査を実施 この中から主な結果として挙げられるのが ①虫歯を持つ割合 5歳以上10歳未満では処置歯まだは未処置の虫歯を持つ者の割合は3%を下まわったが、25歳以上では80%以上と高く、特に45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満、65歳以上70歳未満では100%に近かった。 ②現在歯の状況(8020達成者等) 8020達成者(75歳以上85歳未満の数値から推計)は51.6%で、前回平成28年の調査結果(51.2%)と同程度 また男女別に見た20歯以上歯を有する者の割合及び1人平均現在歯数は、65歳以上では女性のほうが高い数値となっている。 ③歯肉の状況 4mm以上の歯周ポケットを持つ人の割合は、全体では47.9%で、高齢になるにつれ増加傾向 ⑤歯をみがく頻度 1 歳以上の者では、毎日歯をみがく者の割合は 97.4%であった。毎日2回以上歯をみがく者の割合は増加を続けており、令和4年では79.2%であった。 ⑥歯科検診の受診状況 この1年間に歯科検診を受けましたかという質問に「受けた」と答えた者の割合は、全体で58.0%であった。 男性では30歳から50歳未満の年齢階級において、歯科検診を受診している者が低い傾向にあった。 ⑦矯正歯科治療の経験 矯正歯科の経験がある者の割合は、全体で7.7%であった。また、50歳未満では2割近くが経験があり、特に10歳以上40歳未満の年齢階級で高く、男女別では女性において高い傾向を示した。 2022年度の政府発表の経済財政運営に関する基本方針、いわゆる「骨太の方針」のなかで、年代関係なく国民全員が定期的に歯科健診を受けることを目標とする、「国民皆歯科健診」制度の検討が発表されています。 現在1歳半、3歳児の健診は市町村の義務、小学生から高校生の歯科健診は学校の義務です。 しかし、大人の歯科健診は義務ではなかったのですが、政府もようやく重い腰を上げたようです。 北名古屋市西之保犬井190 水野歯科クリニック 院長 水野敦之
日本の水道水中フッ化物濃度の高低が子供のう蝕の多さに関連
こんにちは、水野歯科クリニックです。 前回、フッ素とフッ化物の違いをブログに書かせていただきました。 今回はそのフッ化物の応用について説明します。 フッ化物応用は主に 1. 全身応用 経口的に摂取され消化管で吸収されたフッ化物が、歯の形成期にエナメル質に取り込まれ、むし歯抵抗性の高い歯が形成されます。同時に萌出後の歯の表面にも直接フッ化物が作用します。WF・フッ化物錠剤・フッ化物添加食塩・フッ化物添加ミルクが含まれます。 2. 局所応用 萌出後の歯面に直接フッ化物を作用させる方法です。フッ化物歯面塗布・フッ化物洗口・フッ化物配合歯磨剤が含まれます。 の二種類があるのですが、日本では局所応用が行われています。 フッ化物の応用 E-ヘルスネット 出典元:厚生労働省 E-ヘルスネット 日本では全身応用の一つである水道水フロリデーションは実施されていませんが、水道水にはフッ化物がもともと含まれており、水道法の上限の範囲で地域によりばらつきがあります。 水道水フロリデーションとは、飲料水中に存在するフッ化物の量を適正な濃度に調整し、その飲料水を摂取することによってむし歯を予防する方法のことです。 今回、東京医科歯科大学の研究により、 水道法の上限の範囲で、水道水中の天然フッ化物濃度が0.1 ppm高くなるごとに、う蝕治療経験を有する子どもが3%少なくなることがわかりました。 水道水中の天然フッ化物濃度が0.1 ppm高いと子どものう蝕が3%少ない。 出典元: 東京医科歯科大学2023.5.24 https://www.tmd.ac.jp/press-release/20230524-1/ 日本においては、1952年から1965年まで京都市山科地区で水道水フロリデーションが試験研究として行われました。その他に沖縄県(1957~72年)および三重県朝日町(1967~71年)でも実施されていたことがあります。残念なことに現在ではいずれも中止されているので今回の研究は少し珍しいものだと思いました。 ちなみに北名古屋市の令和5年度の水質検査結果です。 https://www.kn-suido.jp/file/c1_suisitu_kekka_r5.pdf 出典元:北名古屋市資料より フツ素及びその化合物 水道法基準0.8mg/l 検査場所 北名古屋市中之郷0.06 北名古屋市高田寺0.06 北名古屋市熊之庄0.09 豊山町豊場0.08 ppmとmg/Lはほぼ同義語です。 濃度を示す単位でppmがありますが、これはmg/Lと同じ意味ですか?出典元:ミヤマ株式会社環境分析&リサーチより http://www.miyama-analysis.net/law/2020/06/no21.php 少し少ないように思いました。 お隣の一宮市では 佐千原浄水場 0.11 常念公園(大江) 0.11 今伊勢中保育園 (水質監視局)0.11 弁天公園(神山) 0.08 北方小学校(水質監視局)0.11 定水寺児童遊園 0.09 出典元:令和5年4月 一宮市水質検査結果より https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/111/2304.pdf 岩倉市では 第1水源 辻田公園 0.13 第2水源 自然生態園 0.13 第3水源 大市場児童 0.12 八剱町水源 八剱中児童0.07 東町水源 白山公園 0.13 野寄町水源 野寄児童 0.15 曽野町西水源 竹林公園0.18 曽野町東水源 第七児童館0.17 岩倉団地 団地21棟 0.14 出典元:令和4年度 岩倉市水質検査結果より https://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/281/R4kensakekka.pdf この調査結果を見て確かに水道水に含まれるフッ化物に二倍近い差があることがわかりました。 しかしながら今回の結果と先ほどの研究結果が完全に一致するとも思えないです。 今後とも研究を続けてほしいと思うことと共に、愛知県でもこのような調査をしていただきたいと思います。 愛知県北名古屋市西之保犬井190 水野歯科クリニック 院長 水野敦之
フッ素及びフッ化物の違いについて
こんにちは、水野歯科クリニックです。 みなさん、フッ素とフッ化物の違いってご存じですか? 巷でよく言われている フッ素は猛毒 これ、実は正解です。 ただし、歯科医院で塗られているフッ素はあれはフッ素ではなくフッ化物と呼ばれるものです。 どういうことかというと フッ素という呼称は原子番号9番の元素及び単体のフッ素分子のことです。 元素単体のフッ素は確かに猛毒です。しかし元素単体のフッ素はとても強い酸化作用があり基本的に単体ではほとんど存在できません。つまり他の元素を巻き込んでくっついてしまいます。 このように2つ以上の元素が結びついてできた物資を化合物といいます。その中ででもフッ素を含む化合物のことをフッ化物と呼んでいます。 そして、実はこのフッ化物こそが私たち歯科医院で使用する“フッ素”の真の姿なのです。 一般の方にわかりやすくフッ素塗布と歯科医療従事者は呼んでいますが フッ素とフッ化物は大きく違います。 歯科医院で使われるフッ化物は主にフッ化ナトリウムで その作用は ①歯の表面を強くする ②歯の再石灰化を促す ことです。 現在市販されている歯磨剤の90%以上にフッ化物がが入っていますが、年齢により推奨されている濃度が異なります。 6ヶ月(歯の萌出)~2歳 使用量 切った爪程度の少量 500~1,000ppm 仕上げみがき時に保護者が行う。 3~5歳 使用量 5mm以下 500~1,000ppm 就寝前が効果的。 歯みがき後5~10mlの水で1回程度洗口。 6~14歳 使用量 1cm程度 1,000ppm 就寝前が効果的。 歯みがき後10~15mlの水で1回程度洗口。 15歳以上~成人 使用量 1~2cm程度(約1g) 1,000~1,500ppm 同上 ※フッ化物濃度1,000~1,500ppmの歯みがき剤は6歳未満の子どもには使用を控えましょう。 厚生労働省 ライオン歯科衛生研究所 歯科医院で使用するフッ素濃度は9,000~123,000ppmです。 高濃度のフッ化物を使用できるのは歯科医師及び歯科衛生士のみですので、より むし歯予防に力を入れたいという方は歯科医院でのフッ化物塗布をオススメします。 水野歯科クリニック 院長 水野敦之
プライベートでのストレスが多いほど口腔トラブル増加?
こんにちは水野歯科クリニックです。 みなさん、定期的に歯科受診をしていますか? お仕事をしている人がプライベートで悩みやストレスを感じる項目が多いほど、口腔内のトラブルが増加することが東京医科歯科大学の調査で分かったそうです。 職場の定期検診ではメタボリック症候群や血圧など全身状態の観察が中心です。 歯や歯ぐきの状態も加えてストレスによる影響をチェックし、従業員の健康保持の向上につなげる経営の仕組みが必要だとしている。 プライベートでのストレスが多いほど口腔トラブル増加 東京医科歯科大が分析 Lab BRAINS 2023.05.04 当院でも歯科医師会を通じて企業検診をしておりますが、やはりみなさん歯が痛くなったり詰め物が取れたりと口の中が不調になってから来院される方が多いです。 私はよく患者さんに 車でもちょっと音がおかしい、など少しのうちに直せば簡単に終わりますが、それを見ないふりをしてしまうとエンジンから煙が出たりと修理費用も時間もかなりかかることになりますよね? 口の中も同じで小さい虫歯であれば少し削って詰め物で済みますが、そのまま放置して神経まで虫歯が進行すると何回も通院することになります。 また、口の中は自分の目ですべて見ることができません。第三者のプロフェッショナルの人(歯科医師or歯科衛生士)に定期的に見てもらうことをお勧めします。 とお話ししています。 私の治療の信条は 抜かないといけない歯は抜くが、それ以外の歯は来ていただいて治療が終わった後は一日でも一本でも長く歯を残す ということです。 これは長く携わってきた予防歯科からの考えです。 お口の中のお困りごとや相談はいつでも承ります。 詳しくはお電話やメールにてお願いします。 愛知県北名古屋市西之保犬井190 0568-90-5880 院長 水野敦之
唾液について
おはようございます。 年が明けてもまだまだ寒い日が続きますね。 本日は昨年のブログで書いた唾液についてもう少し掘り下げてお話ししたいと思います。 昨年のブログでキャブ・リンシングについて投稿しましたが、皆さんは唾液についてどのくらい知っていますか? 唾液は汚いものと思われがちですが、唾液の約99.5%は水分でできていて残りの約0.5%は無機成分としてカルシウム、リン酸、ナトリウムなど、有機成分としてムチンや抗菌・免疫物質などが含まれています。 唾液の作用はいくつかあり、すべて人間にとってなくてはならない作用です。 湿潤作用 抗菌・免疫作用 自浄・洗浄作用 潤滑作用 粘膜保護・修復作用 溶解作用 消化作用 緩衝作用・再石灰化作用 この中で歯科医院でよく言われるものが緩衝作用です これは食べ物を食べて口の中が酸性になっている状態を中性に戻すという作用です 下の図は歯科医院でよく使われるステファンカーブと言われるものです 食べ物を食べてからすぐに歯を磨かないほうがいいと言っている方の根拠はこれなのですが、正直あまり関係ないと思っています。 それよりも唾液の力で中性に戻りきる前に何かを食べる。つまりダラダラ食べ(間食)が多いと同じ食事をしていてもより虫歯になるリスクが増えます。 また、最近では抗菌作用の他に抗ウイルス作用や抗ガン作用もよく言われており、若返りホルモンであるパロチンも唾液に含まれており、パロチンがたくさん出ると、筋肉・内臓・骨・歯などの生育・発育が盛んになり、若さを保つことにも一役買っています。 よく患者さんから口の中が粘っこくなる。乾いた感じがする。こういう言葉を耳にします。 どうしても年を重ねるにつれて唾液腺(唾液を作る工場)から唾液が出る量が減るので年齢のせい。と言いたいこともありますが、ほかにも 全身性疾患 心理的要因 放射線治療 内服薬 など このように様々な要因があるため一概に加齢変化のためとも言い切れません。 ただ、唾液の量が少なくなると先ほど説明した作用が少なくなり口の中にトラブルが増えることにつながります。 例えば物が食べにくい、飲み込みにくい、会話がしづらい、口内炎がよく起きる、口臭がきついといわれるようになった、虫歯が増えたなど 口の中のすべてを自分の目で見ることはできません。 プロフェッショナルの第三者(歯科医師や歯科衛生士)の目でにしっかりと口腔内ケアと管理をすることがこれからの人生の質(QOLクオリティーオブライフ)にもつながっていきます。